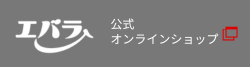ひと手間で、鍋の味がぐっと深まる、
だしのとり方

調味料の計量が必要なく、手軽に使える鍋の素。そのまま使えるストレートタイプ、味の濃さを調整しやすい瓶タイプ、1人鍋に最適なポーションタイプなど、さまざまな商品があり、家族構成に合わせて無駄なく、たくさんの味を楽しむことができます。
そのままでも十分おいしい鍋の素ですが、ひと手間加えることで、飲み干したくなるほどおいしいスープに仕上がります。
今回は、昆布や鰹節などの定番だし以外で、鍋料理にこそおすすめしたいだしをご紹介します。
飛魚(トビウオ)は、海面よりも上を飛ぶため運動量が多く、ほかの魚に比べると脂肪分が少ないのが特徴です。脂肪分が少ないと青臭さが少なく、料理との相性も良いとされています。
主に九州や東北地方の日本海側で飛魚/あごだしが多く使われており、長崎県五島列島の名産「五島うどん」のつゆとして有名。山形県では酒田市の飛島産の飛魚のだしで作られるラーメンが人気です。
焼いた飛魚から本格的にだしをとるのが一番のおすすめですが、だしパックや粉末ならば手軽に取り入れることができますよ。

より強いだしのお鍋にしたい時や、ほかの和食料理に使用する時は、焼き飛魚を浸けたまま中火にかけ、沸騰する前に火を止めて、5分ほどおいてから飛魚を取り出せば完成です。

少し贅沢をしたい時の魚介系のお鍋には、ホタテが欠かせない具材です。生のホタテを丸ごと使っても、刺身用の貝柱をスライスしてしゃぶしゃぶのようにしてもおいしく召しあがれます。ホタテは少しの量でも豊かな香りが広がり、だしに深い旨みを加えてくれる、うれしい具材です。
なかでも、お酒のつまみとしてそのまま食べることの多い「干し貝柱」が、2つ目のおすすめだしです。高価ですが、だしをとった後はそのまま鍋の具材として食べられるので、無駄もなく、ほかの食材では代え難い味わいを楽しめます。
温めるだけで立派なおかずになるさつま揚げ。炙り焼きや煮物などの和食に活躍するさつま揚げは、おでんの人気具材でもあります。
鹿児島や長崎など本場のさつま揚げは、魚のすり身に練り込まれている野菜もさまざまで種類も豊富。明太子入り、ジャコ入り、なかにはちゃんぽん味などもあり、味の違いを楽しむことができます。
お鍋に使えば、だし・調味料・具材の三役をこなすさつま揚げ。できれば2種類以上のさつま揚げを使って、独自のだし作りを楽しみましょう。

まとめ
「だしをとる」といっても、飛魚だしも干し貝柱だしも、ただ水に浸けておくだけ。今晩はお鍋!と決めたら、朝のうちに水に浸して冷蔵庫に入れておけば準備完了です。
手間は少なめですが時間はかかるので、一度で多めのだしをとり、煮物や酢の物の三杯酢、だし巻き卵などに活用するのがおすすめです。また、冷蔵庫で保存すれば、3日間ほど風味を楽しめますよ。

短大卒業後は保育園に就職。約4年半、栄養士として給食業務に携わる。
その後、大手GMSの食育運動に約2年携わったのち、大手総合卸会社に転職後はSMやデパ地下のメニュー提案、商品開発の業務を約4年半行う。
その後、2010年祐成クッキングアートセミナーにてフードコーディネーター養成コース卒業、翌年2011年管理栄養士資格の取得。
現在は特定保健指導や企業向けにフードスタイリング、レシピ開発、メニュー提案などを行っている。
5歳と3歳の子供を持つ。


 エバラ通販サイト
エバラ通販サイト